読書のページ
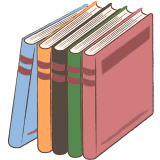 このページでは最近読んでいる本について記していきます。気が向いた時に更新。以前の記事は消去していきます。
このページでは最近読んでいる本について記していきます。気が向いた時に更新。以前の記事は消去していきます。
『西洋の敗北と日本の選択』エマニュエル・トッド著、文春新書、2025.9
雑誌に収録されたもの。および対談集という内容である。『西洋の敗北』の続きになっているが、現在世界で起きていることを鋭く分析したものだと思う。ただ「日本は核武装せよ」という考え方は私としては少々疑問だった。面白かったのは「イーロン・マスクは『道徳破壊』の象徴」のところで、キッシンジャー元米国務長官に関する笑い話のところ。内容はここでは書かないがこういう小話が私は大好きである。(2026.1.14)
『西洋の敗北 日本と世界に何が起きるのか』 エマニュエル・トッド著、文藝春秋、2024.11
全413頁とかなりの大著で、読むのに時間がかかった一冊。ロシア、ウクライナ、そしてヨーロッパについてかなり深く理解することができたと思う。2025年12月16日現在、 「ウクライナが『安全の保証』条件にNATO加盟断念も…ロシアとの和平案協議で妥協姿勢示す」というニュースが報じられているが、その昔、単に武力による領土拡張主義はけしからん、と思っていた私にとって、ヨーロッパとロシア、そしてアメリカの関係をもっと勉強しなければ簡単に意見など言えたものではないことに気付かされている。そして著者が「なぜ西洋は、自らの敗北を認めようとしないのか」という言葉の意味は重いと思う。 (2025.12.16)
『第三次世界大戦はもう始まっている』 エマニュエル・トッド著、文春新書、2022.6
購入したのはかなり前であるが読んでいなかった本。なぜ読まなかったのかはよく分からないが、たぶんコロナ禍の中でオンライン授業だとか催し物の中止などが相次ぎ、そちらのほうで忙しかったためと思われる。読んでみて、現在の世界状況を考えるうえで非常に参考になる内容だった。人類学的な見地から色々な国を考えている点が特に印象に残る。たとえば「西洋社会はみずからを普遍的だと思い込んでいるが実は特定の家庭構造に組み込まれている」という所である。その他、現在の世界を見る際の考え方のヒントをたくさん得ることができた。次は同じ著者による『西洋の敗北』を読む。(2025.10.28)
『べートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』 かげはら史帆著、河出文庫、2023.11
知人から同じタイトルの映画を見ましたとの連絡を頂き、かつて書店でこの本を見たことを思い出した。シンドラーがべートーヴェンの会話帳のある部分を処分してしまったこと、あるいは改竄したということについては知っていたので、目次を見ただけで購入しなかった。ただ、10月に講演会でこの作曲家のことを取り上げる予定なので新しい情報は仕入れておくべきだと思って文庫版を購入したのである。結論から言って、予想をはるかに超えた面白さであった。史実にも基づいているし、詳細な註も充実している。「衝撃的歴史的ノンフィクション」と背表紙に書いてあったがまさにその通りだと思う。面白かったのはシンドラーの視点から書かれている点と、セイヤーが真実に迫っていたのか、という問いが投げかけられている点だ。栗原康氏による解説も素晴らしい。その後映画も見たが、こちらも非常に面白かった。「脚本:バカリズム」とあるので喜劇を想像していたがそんなことはなく、「大河ドラマ的に語る」べートーヴェン伝はいったいどんな意味を持っていたのか、ということを考えさせてくれるものだった。「名プロデューサーは嘘をつく」とあるが、確かに私の知っている人にも[自ら捏造した]偽情報をいかにも真実のように語る人がいたことを思い出す。人間とはいつの世もこのようなことをするのかもしれないというのが 率直な今の感想である。(2025.9.27)
『決定版 交響曲の名曲・名演奏』 許光俊著、講談社現代新書、 2025. 2
この著者の音楽評論は何冊も読んでいる。結構クセが強く個性的だなと思っていたのだが、今回は歴史を踏まえた上で名演奏について書かれた内容で、なかなか興味深く読んだ。ハイドンについてなど勉強になったし、べートーヴェンとヘーゲルについての考え方の共通点などを読むと「なるほど」と思わせられるものがある。さらに印象に残った部分はメンデルスゾーンの交響曲「スコットランド」について書いてある所、それとブルックナーの初稿について書いてあるところである。指揮者とオーケストラについてはあまり深く考えてこなかった私ではあるが、今後はもっといろいろな観点から鑑賞を行いたいと思った。(2025.9.9)
『世界のニュースを日本人は何も知らない 6』 谷本真由美著、ワニブックス、2024.12
このシリーズは5作まで読んできて、今回も非常に興味深く読んだ。特に第4章「パリオリンピック騒動から学ぶフランスの戦略」「フランスとは戦略がちがうイギリス」が面白かった。民族、国により考え方や行動はかなり異なるが、そういうことをもっと知る必要があると思う。それと「テレビに出ている学者を評価する方法」。なるほどと思わせられる記述だった。(2025.9.3)
『暗殺』 柴田哲孝著、幻冬舎、2024
この種の本を読むときはノンフィクションに限っていたのだが、「この物語はフィクションである」と最初に書かれている内容である。結論から言うと非常に面白く読んだ。元総理が凶弾に倒れた事件はまだ記憶に新しいが、以前からおかしいなと思う所はあったので、そのあたりを考えさせる内容となっている。今でもSNSなどでもその辺りについて述べる人がいるので、興味をもって読んでみたという次第である。銃について書いてある部分は少々専門的で分かりづらいところもあるが、話の進展はなかなか面白かった。(2025.9.1)
『史料で読み解くべートーヴェン』 大崎滋生著、春秋社、2024
仕事の関係でべートーヴェンについての本を次々と読んでいるところだが、この書は今までの「楽聖べートーヴェン」の伝説的イメージを払拭させる内容だと思う。いちばん衝撃的だったのはシンドラーによる「旧べートーヴェン像」の問題を史料からしっかり論じていることだった。シンドラーは晩年のべートーヴェンのことをよく知っていた人だと思っていたのだが、大崎氏によれば彼がべートーヴェンの側にいたのは15か月ということだそうである。それと「エロイカ」シンフォニー(著者は「交響曲という名称を使わない)とナポレオンの関係について。さらに終章「音楽学とは何か」。かなり多くの発見があり、研究とはこのように行うものだということを教えてもらった思いがする。同じ著者の「べートーヴェン像 再構築」はかなり高価な本なので購入には躊躇しているところだが、いずれ読んでみたいとは思っている。(2025.8.4)
ところで、これはこの本に限ったことではなく最近の雑誌などでもしばしば見られるのだが、「すべからく」の誤用と思われるものがある。例えば「シンドラー後の伝記的記述はすべからくそれに汚染されていた」。この語は「(多くの場合、下の[べし]と呼応)なすべきこととして、当然(広辞苑より)」という意味なので本来の使い方は「シンドラー後の伝記作家たちはすべからく過ちを正すべきである」などという言い回しが予想されると思う。これを「すべて」の意味で使うことについては『三省堂国語辞典』に「②[俗]すべて」とあり、この語の由来は「そうすべくあることには」という意味の古語からで「すべて」とは語源がちがう、と書かれている。こういうことについて私も注意したいとは思っている。(2025.8.5)
『べートーヴェンの生涯 』青木やよひ著、平凡社新書、2009
大作曲家についてのこの名著を再度読み直している。有名なのは「不滅の恋人」についてアントーニア・ブレンターノ説を世界で初めて発表したということで、これはこの本を読むまで知らなかった。べートーヴェンの伝記の中では最も優れていると読んだ当時は思ったものだが、現在は神聖ローマ帝国が崩壊していく過程を調べているので、その当時のオーストリアの政治状況も考えながら読み直しているところである。驚いたのは、「あとがき」にある2009年11月という日の翌月(同年12月)に青木氏がお亡くなりになっていたということだ。著者自身の病との闘いの過程で「生涯病に苦しんだべートーヴェンをより深く理解する視点が獲得できたのではないかと感じている」とある言葉は重く受け止めたいと思っている。(2025.7.19)
『哲学するべートーヴェン カント宇宙論から《第九》へ』伊藤貴雄著、講談社選書メチエ、2025
べートーヴェンの音楽ノートにカント哲学書からの引用があることは知っていたのだが、彼がボン大学で哲学をどのように学んだかについてはよく分かっていなかったので、非常に興味深く読んでいる。今まで読んだ音楽書とは違った情報がある本だと思う。たとえば当時の社会が絶対王政から人間の理性を重視するようになっていたという点で、世界史では習ったのだが、それが音楽および音楽家とどのように関係しているのか、という点について実はあまり考えていなかった。ネーフェがボン支部の責任者を一時務めていた友愛結社「イルミナティ」については初めて知った次第である。それにしても現代では「哲学」はあまり語られなくなったように思う。その辺も考えながら読んでみたい。(2025.6.22)
ボンの「読書会」や大学聴講生としてのべートーヴェンについてはセイヤーの著書、あるいは平野昭『作曲家◎人と作品 べートーヴェン』などにも書いてあったのだが、今回はより詳細な知識を得ることができた。それと「ハイリゲンシュタットの遺書」とカントの『人倫の形而上学についての基礎づけ』との関係については非常に興味深く読んだ。(2025.6.24)
『西洋の自死 移民・アイデンティティ・イスラム』ダグラス・マレー著、町田敦夫訳、東洋経新聞社、2018
移民問題がヨーロッパでいろいろ報じられていることは知っていたが、日本でも最近は「多文化主義」の問題が語られるようになってきている。この本を読んで思い出すのは、2020年7月26日に産経新聞に寄稿された飯山陽氏による「『多様性』に隠れた不公正」である。「特定の少数派に対する特別扱いは、多数派の人々に不平等感、不公平感を引き起こし、それは集団の分裂、対立の呼び水となるという側面もある」という意見にはなるほどと思わされるところがあった。本書からも、多様性を認めることは一応大事として、社会を維持するためにそれをどの程度にするのかというのは結構大変な問題だということが分かる。現代は「分断」という言葉をよく聞くようになっているので、その辺について今後も考えていきたいと思った。(2025.6.17)
『街場の五輪論』内田樹・小田嶋隆・平川克美共著、朝日文庫、2016
内田氏の書いたものは何冊か読んだが、最近の日本で報道されるニュースがどうもおかしな方向のものが多くなっているように思い、昔の本を読んでみた。まず「プロローグ」で「五輪開催によって日本社会のさまざまなシステムの劣化と崩壊は加速するだろう」と野生の勘が告げていると書かれている。ずいぶん前に読んだ本であるが、私も2020年の東京オリンピックが開催ということになった時は何か違和感をもっていた。その時感じたものが現在でも続いているように思う。たしかに「無言の同調圧力」はどの時代にもあるだろう。ただ、「原発はアンダーコントロール」という言い方に反対する人がマスコミにはほとんど出てこなかったことに何か不安を感じていた私としては、この本に書かれていることには納得できる部分がたくさんある。
(2025.6.9)
『動乱期を生きる』内田樹・山崎雅弘共著、祥伝社新書、2025
対談形式で書かれた本である。まず「はじめに」で“身体実感”という言葉に共感を覚えた。「言っていることは筋が通っているようだけれど、聴いているうちに鳥肌が立ってきた」というような経験のことと書かれているが確かにそういうことは以前にあったように思う。明らかにこの人は虚偽を述べているのだが非常にもっともらしく聞こえるというような・・。第1章では「倫理的崩壊の危機」について書かれているが、内田氏が言う「焦点距離の伸縮」という視点は分かりやすい。現代ではいろんな分野で劣化が進んでいるというのはまさにその通りだと思う。第2章は「地に落ちた日本の民主主義」というタイトル。日頃感じている政治家の言葉について「パワークラシー」という言葉が出てくる。主権者が「すでに権力者にあるもの」という単純な理屈。本当にそんな国になってしまっているのだろうか。今日買った本なのでとりあえずここまでにしておく。(2025.5.28)
第3章は「教育システムの機能不全」で、この分野に長くかかわってきたので興味深く読んだ。特に中高6年間で「個として独立した思考」が失われていくという指摘、そして「トップダウンの集団は非常時に弱い」というところが印象に残った。何だか読んでいて将来に対して暗い気持ちになってしまうがこの先に希望はあるのだろうか、と思う。(2025.5.29)
第4章「動乱期に入った世界」、第5章「自ら戦争に歩み寄る日本」まで読んだ。ウクライナとガザで起こっている戦争では「軍事行動のルールが変わった」とあるがなるほどと思う。国連や国際法の意義が何だか薄れているなあとは思っていたのだが、なぜそうなっているのか今後も考えてみたいと思った。そして「近い将来、日本が戦争に巻き込まれる可能性」について書かれている。何だか怖い話であるが、起こりうることについて色々な角度から考えてみることが必要だとは常々思うところである。英米の作家たちは「絶対にこんな未来が来てほしくない」と思うとそのディストピアについて想像力を駆使して物語を書く傾向がある、と書いてあった。そういう「表と裏から」考える姿勢が必要であることを再認識した。(2025.5.31)
第6章は「2024年の衝撃」で、トランプ大統領が再選されたこと、日本での選挙のあり方が変化してしまったことなどが取り上げられている。メディアの劣化について書かれている部分で、ドラマで新聞記者やディレクターを取り上げたものが無くなったとの指摘はなるほどという感じだ。第7章は「思考停止に陥る前にできること」。英語教育の目標がオーラルコミュニケーションに偏っている点については全く同感だった。今回の読書は、日本及び世界の政治について、そして社会について普段気になっている問題点が「なぜそうなったのか」を考えることが出来たきっかけになったと思う。(2025.6.1)
『分析的演奏論 人間の光と影』ヒューエル・タークイ著=三浦淳史訳、音楽之友社、昭和48年
ある音楽評論を読んでいてこの本の引用があり、非常に興味を持ったためインターネット古書店関係で入手した一冊。巻末に「掲載紙一覧」があり、「音楽の友」「レコード芸術」「週刊FM」などに掲載されていた文章であることが分かる。著者名を覚えているので一度は読んだことがあったのかもしれない。大指揮者の逸話についてはある程度知っていたが、この本に書かれた内容からはかなり音楽家の人間性を知ることができた。アメリカに音楽市場が成長し、ヨーロッパでの二度の対戦で音楽文化が変わってしまった中で、個性派人間がどのように音楽と向き合っていたのか、いろいろ考えさせられる内容だと思う。特にクレンペラー、ライナーについての記述が面白かった。(2025.4.29)
『揺らぐ日本のクラシック 歴史から問う音楽ビジネスの未来』 渋谷ゆう子著、 NHK出版新書、2025
地方に在住していると、そして年齢的に若い頃のような好奇心も乏しくなっていることもあり、最近は音楽会に出かけなくなっている。世の中全体にそんな状況があるのだとしたらその原因は何だろうか、という問に対する答えがあるのなら知りたいと思って購入した。内容は「歴史から問う」とあるように音楽界の歴史について書かれた部分が多い。欧米についての記述は参考になった。ただ、最後のところで「いくつかの戦略」があると書かれているが、「まずひとつは、興業とアウトリーチを密接に絡めること」とあり、それについては理解できたが、二つ目(あるいはそれ以降?)がよく分からなかったのは残念である。「地方でのクラシック音楽の土壌について」というところがそれにあたるのかもしれないが、「いくつかの戦略」とあるので「二つ目は」「その次に」などの言葉を期待して読んでしまう。これは長年、論文指導なども行ってきた私の悪い癖なのかもしれないと思っているところである。現代は、音楽を聴こうと思ったらYoutubeなどで簡単に視聴できてしまうということが最も根本的な問題だと思っているので、多くの演奏家や音楽大学などは存在価値を失いつつあるのかもしれない。そうすると、職業音楽家を目指すことへの警告などといった内容の著書があれば今後読んでみたいものだ、と勝手なことを考えてしまった。(2025.4.1)
『バルトーク 民謡を「発見」した辺境の作曲家』 伊東信宏著、中公新書、1997
バルトークのピアノ作品は 「ルーマニア民俗舞曲集」「子どものために」「ミクロコスモス」「ソナチネ」「15のハンガリーの農民の歌」くらいしか知らなかったことを最近反省しつつ、彼について書かれたものを一つ一つ読んでいるところである。まずは洋書で Klaus Wolters “Handbuch der Klavier-literature から読んだ。ハンガリーのピアノ曲について書かれた箇所である。さらに、買ってはいたが全然読んでいなかった『西洋の音楽と社会(総監修・スタンリー・セーディ、全12巻、音楽之友社)』の第8巻を読んでいる。それと並行して標記の著書も読んでいるところだ。こういう読み方が私の流儀で、複数の本を比べながら読むのである。本日は第1章まで読んだのだが、これはかなり面白い内容である。最初にシェーンベルクの言葉が引用されておリ、ハプスブルグ帝国から見た「文化的に独立の機が熟していない小国」という表現が、19世紀末の時代を感じさせる。そして、民族性とは何かという重要な問題について。これは「デオダ・ド・セヴラック 南仏の風、郷愁の音画(椎名亮輔著、アルテスパプリッシング)」でも指摘されていたことで、以前からこの点について興味があった。19世紀の「ハンガリー音楽」はやはりチャールダーシュのイメージが強かったことも書かれており、一時的に愛国主義であったバルトークが科学的関心による民族音楽研究へと変化したことが書かれている。以降も楽しみに読んでいきたい。(2025.3.1)
第3章「民謡コレクション『ハンガリー民謡』を読む」の中で2か所、興味深い記述があった。ひとつは「以前ハンガリーの右翼的勢力から非愛国的であると非難されたその同じ論文が、今度はルーマニア人から親ハンガリー的であると非難されることとなった」というところで、これは1920年のヴェルサイユでのトリアノン講和条約」によりハンガリーの領土が3分の2となったことと関係している。もう一つはバルトークが行った民俗音楽研究「ハンガリー民謡」が完全な分類学であり、19世紀の博物学の伝統に根ざしているというところだ。博物学と言えば阿部謹也ほか著『いま「ヨーロッパ」が崩壊する』を思い出す。山口昌夫「ヨーロッパを支えた『隠れた知』とは」の中で、日本の博物学が廃れた経緯について書かれているのだが、博物学がヨーロッパで成立したのはルネサンス前後のことであり、「集めることによって成立してくる知の形態」という言葉があった。これはなかなか面白い考え方であり、ヨーロッパの「隠れた知」を日本の近代では学ぶことを怠ったという指摘には考えさせられるものがあると思う。(2025.3.4)
BACK
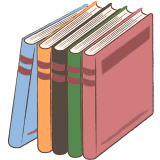 このページでは最近読んでいる本について記していきます。気が向いた時に更新。以前の記事は消去していきます。
このページでは最近読んでいる本について記していきます。気が向いた時に更新。以前の記事は消去していきます。